2005-06-21
ビブリオサライ 第2回セミナー
講師:吉岡逸夫さん(ノンフィクション作家・ドキュメンタリー映画監督・新聞記者)
◆2005年6月20日(月) 於:飯田橋・家の光協会 1階セミナールーム
吉岡さんは東京新聞社会部記者として活躍する一方で、これまでにカンボジアやルワンダのPKO、アフガニスタンやイラクを取材、また世界各地の青年海外協力隊員を訪れるなどして、精力的にノンフィクション作品を発表してきました。さらに近年は、ドキュメンタリー映画の分野にも進出し、大きな反響を呼んでいます。今回のテーマは、ノンフィクションの出発点となる《取材現場》。ご自身の体験をベースに、なぜ《戦場》に呼ばれてしまうのかなど、リアルなお話をお伺いしまた。
今回はイラクで拘束された郡山さんたちを追ったドキュメンタリー映画『人質』を、講演に先立ってビデオ上映しました。
◆ドキュメンタリー映画『人質』について
■『人質』のできるまで
この映画は去年(2004年)の夏に撮ったのですが、最初は(イラクで人質となった)郡山総一郎さんの講演会に行ったときに彼と話していて面白いなと思い、その後郡山さんに声をかけました。報道されたもので持っていたイメージと全然違って、それと現実とのギャップが面白かった。それはそのまま映画になるかもしれないと思いました。
当時、マスコミの彼らに対するバッシングがひどかったのですが、名刺交換したら彼が僕のことを知っていたんです。「吉岡さんの本、読んだことあります」って。それで何日かして新宿のゴールデン街で話しました。そのときに僕はもうカメラを持っていましたけど。雑談している段階で「こういうので映画撮るんだよ」って言いながら撮り始めていた。
話しているうちに、「これ、本にしないの」って聞いたら、時間がないということだったので、「僕が話を聞こうか」と言ったら「助かります」と。それで、僕の知っている編集プロダクションに企画書を作ってもらって翌日に流したら、その日のうちに出版が決まりました。
そうして『人質』というインタビュー構成の本が去年出たのですが、せっかく話してもらうのだからとついでに撮ったものです。全部で3日間にわたって10時間くらいインタビューしています。手持ちのカメラと、もう1台、三脚に付けっぱなしにしていました。2カメあったほうが変化もつくし、ビデオチェンジの間をもう1つのカメラが押さえているという意味で使いました。
制作費は、ほとんど編集費で12万円くらいです。僕の作る映画の制作費は10万~20万円くらい。20万円を超えたことがないんです。もし自分でパソコンを使って編集できれば、数万円でできると思いますけど。
■現実とメディアの二重性
この映画は基本的にインタビュー構成で、映像的には難しいと思いました。それをどうやって最後まで観客を眠らせないようにするかが演出になるのですが、映画関係者に聞いても、「インタビュー構成はやめたほうがいい」という意見ばかり。そういう意味では映画になるのかという怖さがずっとありました。
ただ、映画というのは音声と画像の二重構造になっています。だから、彼の証言が音で流れて、画面には新聞なり雑誌の見出しを出すことで、現実とメディアで伝えられたことという二重構造を表せると考えました。それから、僕が前に行ったイラクの映像を挟む。飽きさせないようにというのもありますし、イメージをつかみやすいということもあるので、できるだけ自分が撮ったイラクの映像の中から使えるものを出してきました。
それからこれはいいなと思ったのは、終わり近くの新宿のトンネルを行くシーンです。あれはインタビューした日に彼を駅まで送っていく途中を撮っていたのですが、トンネルの中に入ったときに音楽が聞こえてきて、「ああ、これはそのままラストシーンだな」と思いました。彼を見送った後、急いでトンネルに戻ってもう一回録音させてくれと頼んだんです。そこで録音したものを、最後にもう一回、タイの映像にかぶせました。
その後に郡山氏がタイに行くというので、僕も一緒にいきまいた。そのときのシーンで終わらせるつもりだったけれど、あるプロデューサーに見せたら「これじゃ郡山氏の青春映画じゃない」みたいなことを言われたんです。
僕はそれでもいいと思っていたのですが、人質事件についてもう少し分かるようにと、最後は「自分が登場してしまえ」とラストを作りました。僕自身もメディアであるという皮肉を込めて入れたんです。
■「逃げ」の気持ちがあってもいい
イラクでボランティアをしようという人たちの気持ちには、逃げという面もあるかもしれません。僕も昔、リュック背負って安宿に泊まりながら放浪していたことがありますが、自分で分かっていました。日本からの逃げだって。日本が嫌で嫌でしょうがないから、日本なんか帰って来ないと思っていた時期もありました。だから、逃げということもあり得ると思います。
イラクに限らず、日本が嫌になったら旅行に行ったりするし、音楽を聴くのもそうだけれど、ひとつの異次元というか、非日常の世界に入ってくというのは、逃げであるけれども必要でもあるんです。非日常の中にときどき入っていかないと、毎日働いてばかりの日常というのはしんどいですよね。
僕は取材で外国に行ったりするけれど、そういう意味で気分がハイになる。取材というのは表向きで、内面では逃げだったり、そういう異次元に入る楽しさがあると思います。あの人たちもイラクに行ってボランティアをしようというパワーもありますが、内面では日本からの逃げということもあるかもしれません。もし、そうであったとしても悪いとも思わないし、自然なことだと思います。
■メディアが作った人質騒動
一連の人質騒動は、マスメディアの「自作自演」という言い方がいいのかどうか分かりませんが、メディアが作っているだけだと思いました。というのはイラクに行ったことがある人なら分かるけれど、人質が捕まったというときに「でも殺さないよね、イラク人は」みたいな感覚です。最初はそんな大きな事件とは感じなかった。それどころか、イラクにいたジャーナリストは、「あいつら、いいな」と思ったとしても不思議ではないです。あのころ現地にいたジャーナリストは何を取材したかったかというと、アメリカに対して戦っているイラク人を知りたかった。だから人質にとられたということは取材対象を目の前にするわけですよ。それはスクープになり得ますからね。
(郡山さんたちの事件の後、イラクで拘束されたジャーナリストの)安田純平氏は捕まっても殺されないと実感していて、現に解放されたとき、「次、また来るね」と言って、彼らも「また来てよ」と別れてきた。それくらい仲がよくなっちゃうんですよ。それで大騒ぎするわけですから、「おいおい、どうなってるんだよ」と感じました。
なぜメディアがこの事件を作ったかというと、家族の記者会見です。僕の感覚では、家族の記者会見は必要ない。今井君は未成年だけど、あとの2人は成人ですから家族が出てくる必要もないし、自己責任を言うのであれば家族は関係ないんです。外務省は自分たちの仕事をやればいいだけの話です。
新聞も、一面に大きく載せなくてもいい。それ以前にも社会面の片隅に「ジャーナリスト行方不明」なんて載っていたりしましたが、それくらいの記事でよかった。
だけど、アルジャジーラが放送して自衛隊の撤退要求があった。それが大きく報道されて、家族も泣いたりするから、さらに大きくなります。メディアというのは喜怒哀楽を出すと、視聴率が取れるし、新聞も読まれるので、一番おいしい。だからどんどん使う。
でも、あれは使わなくていいんです。ああいう部分は、冷静に考えたら報道とは関係ないわけですよ。家族が泣いたり喚いたりするのは当たり前のことですから。僕から見ると、正常なメディアならああいうシーンは使わないし、記者会見は最低限でいいと思う。それをああいう風に煽り立ててセンセーションにもっていけば売れるという商業主義があった。
一方で市民の側はどうかというと、あの事件の特徴は、3人が個人で動いていたということです。今までの外国での邦人人質事件は企業や国が派遣していたケースばかりでした。
でも、今回は個人で行っていた。日本人は個人で行くということにはけっこうアレルギーがあるみたいで、勝手にやっているという感じだった。日本人はそういうことが嫌なんでしょうね。おそらく嫉妬もあるだろうし、個人で動くことがわがままであるとか、勝手だとか、そういう気持ちがあったのかもしれません。
海外の人質事件では、家族が出てくる場合もあるけれど、バッシングすることはないですよ。そこは日本の特性でしょうね。今まで培って部分、一緒に田植えをやって労働して村を築いてきた日本人の文化的な部分です。
そこで個人行動や、自分で考えて何かやる人間というのは排除しようとする気持ちがあるのかなという気がしますね。そういうのは第二次世界大戦で終わっていると思ったら、いまだにそうなんだなというのが僕の感想です。
◆ノンフィクションの現場
■戦場カメラマンの教え
僕は報道カメラマンとかジャーナリストになろうという気持ちは、22歳までまったくなくて、コマーシャルでもやるんだろうなと思っていました。海外協力隊でエチオピアのテレビ局にいたのですが、そのときにベトナム戦争で活躍した岡本昭彦さんという報道カメラマンに会ってぼろくそに言われたんです。「君はテクニックを先に覚えているから報道をやってはいけない」と。
写真学校に行ってテクニックは知っていました。でも世界がどうなっているとか、岡村氏のような知識はないものだから、彼はそう言ったわけです。彼は「シャッター以前が大事だ」ということを言っていますから。
それでもこの世界に入ってきたのは、それに対する反発で、「冗談じゃねえよ、俺でもできるはずだ」という気持ちがあった。
それからもうひとつは、反発を覚えながらも彼を尊敬していた面があったんです。彼の尊敬すべきところは、ベトナム報道をやったときに、日本では北ベトナムに回った人はいなかったんですが、彼は両側から撮らなくてはいけないと北に回った。そうしたら捕まってしまってカメラも全部取り上げられたんです。
そのときの記事を『ライフ』に発表したのですが、写真を撮れなかったのでイラストが載っていました。それも自分が書いたものではなくて、アメリカ人のイラストレーターに指示して書かせたものです。それで僕はびっくりしました。この人はカメラマンなのにイラストで発表していると。
彼はその後、南ベトナムが陥落してから最初に入って行ったときも、レポートを雑誌『世界』に書いています。「フォトドキュメント 北ベトナム再訪」と書いてあった。ところが写真が一切ない。全部文字なわけ。何でかといったら写真を撮っちゃいけないと言われて彼は撮らなかった。それで全部文字で書いて、タイトルはフォトドキュメントとある。
「いやあ、すげえなあ、確かにそうだ」と思いました。ジャーナリストというのはカメラマンになりたいとか、ライターになりたいとかではない。伝えることがジャーナリストなんだから、自分はカメラマンであるとか、記者であるとか、イラストレーターであるとかというのはどうでもいい。原理原則を考えてみれば、自分が持っているもののできる範囲で伝えればいいだけの話であって、それが僕にはずっとベースとしてあったんです。
■カメラマンから記者へ
その後、東京新聞名古屋本社、中日新聞にカメラマンで入ったのですけど、その前に業界紙にいてライターをやっていたんです。業界紙のときは、企画から写真撮って記事書いて広告取りまでやって、全部やっていたんですよね。いちおう一通り覚えたわけだけど、新聞社入ったら写真だけ撮ればいいわけです。何だかすごい楽だなと思った。時間も余っちゃうし。それでときどき書いたりしていました。
それでもいろいろなヒエラルキーがあって、書かせてもらえなかったり、嫌味を言われたりしましたけど、東京へ来てから、東京本社は人が足りないから書いたら喜ばれる。それでどんどん使ってくれるから、なんとなく覚えました。
それから本腰を入れて、カメラマンを辞めて記者に行くぞと思ったのが、カメラに飽きたのと同時に、カンボジアPKOの取材に行ったときに自分の写真というのが見えたんです。ここが僕の転機だったのだけれど、世界の見え方が変わってきた。
そのときに自分の写真というものが何であるかというのが見えて、自分は新聞社にいたら自分の写真は撮れないと見切りをつけた。それで世の中の見え方が変わったときに、この見え方をそのまま書きたいと思ったんです。今なら書けると思った。
それから会社と交渉し始めて、実際に記者になるのには1年以上かかりました。「何考えてるんだ」と言われて、編集局長に土下座したりして、怒鳴られながらもしょうがないなということになって、横浜支局の警察回りから始めたんです。
記者への異動が認められない間も、フリーという選択肢はありませんでした。フリーには怖くてなれないんですよ。
なぜかというと、僕の親父が商売をやっていて、何度も失敗しているんです。僕にとってはああいう生活は地獄なんです。うちのバロメーターは、商売がうまくいっているときはテレビがある。ダメになるとテレビが消えちゃう。そのときは悲惨ですよ。フリーもある意味、同じようなものですよね。ああいうのがいやだというのがあります。
まあ、会社を首になれば嫌でもフリーにならざるを得ないこともあるんだし、だからできるだけ会社にいようと思っています。
■9.11の衝撃――「やっぱり映像だ」
自分が書けるなと思ったことと、カメラには見切りをつけたことがあって、現実にそれから書き続けられたわけだけれども、会社からアフガニスタンに行ってくれと言われて、そのときにたまたま買ったばかりのビデオカメラがあったんです。
動機には9.11があったんです。9.11の映像を見ていて、「うわ、すっげー」と思いました。目の前であんなことが起きたら、やっぱり映像だよなと。それで量販店に行ったら、8万円だった。あ、10万しないんだと思って買ったんです。それをたまたまアフガンに持っていったけど、最初はパキスタンで時間が余って、やることがなくてそれで遊んでいた。記念に撮っていたけれど、どうせ撮るならテーマを決めて撮ろうと思ったんです。
仕事に差し支えないように、『なぜ記者は戦場へ行くのか』というのをテーマにして、本にもなりましたけど、「なぜアフガンへ行くのですか」「怖くないですか」「命をかけるほどこの取材は値打ちがありますか」というようなことを聞きながらアフガンに入っていきました。周りに記者は何百人といるわけだから、空いた時間に聞いて回って、撮りました。
日本に帰って、日本映画学校の安岡さんという先生が前から知り合いだったので、戦場の現場だから「学校の生徒に見せたらいいと思うよ」と彼に見せたんです。それを「面白いな、これ劇場でやろうよ」と言い出して、BOX東中野で上映しました。人がけっこう来たので、自分でも驚いたんですけど、これでいいのかなという思いもありました。
そのうちイラクへ戦争前に行く機会があったんです。NGOと一緒に10日間だけ行って、やっぱりカメラを持って行きました。アフガンのときは仕事の邪魔にならないように、空いた時間に映像を撮っていたんだけど、イラクに行ったときにちょっと考えが変わって、テープレコーダー代わりに撮ればいいんだと思いついたんです。だからイラク人にインタビューしている間、ずっと回していました。
テープ代わりに撮っていて、これは情報が多くていいやと思っていた。それで、夜になると巻き戻してテープ起こしみたいにして記事も送ったんですよ。日本に帰ってから、やっぱりもったいないから編集してたんですけど、そのときの編集マンが「なんでイラク人ってこんなによく笑うの?」と言い出して、『笑うイラク魂』というタイトルで、インタビュー構成の映画に仕上げたんです。
それで上映して、最初は人が来なかったのが、本当に戦争が始まって、ひとつワイドショーが取材に来たら、皆取材に来るんですよ。映画にもけっこう人が来て、黒字になっちゃった。なんだかそういうことで、自然に映像に入っていったというのがありますね。
■カメラマンが取材した海外ニュース
僕自身、イラクやアフガン、カンボジアやルワンダなど、一般には危険なところに行くというイメージがありますが、希望して行っているわけではないんですけどね。
僕は青年期外協力隊でアフリカに3年近くいて、英語が多少できたんです。新聞社に入った当時は、まだ英語ができるカメラマンがいなかった。それで多少は海外取材の機会が多かったんです。
決定的だったのは、東欧崩壊のときに、サンデー版の企画で「世界のマーケット」という取材で、(カメラマンとして)東欧に行っていたんです。東欧がゴタゴタしはじめた時期で、市場の写真は取材するんだけど、東ベルリンから人が逃げたりとかしはじめて、僕も面白いものだから撮っちゃうんですよね。撮って国際宅急便とか郵便とかで送ったら、本社がびっくりした。「あいつ、企画で行ってるのにニュースを送ってきやがった」って。
そのころは、特派員は別にして、自社の記者が東欧のニュースをじかに取材するなんて思っていなかったわけです。だから、よく使ってくれましたよ。それで「あいつはニュースもできる」ということになって、東欧の崩壊が終わったあと、湾岸戦争が始まりそうだと言うんで、今度は同じサンデー版で「中東へ行ってくれ」と言われました。
戦争が始まったらそちらも取材してくれというわけです。それで、8ヶ国くらい回って、ヨルダンへ入ったら、イラクで日本人の人質が何十人か捕まっていると。
ちょうどアントニオ猪木(当時、衆院議員)が来ていて、朝日新聞のカメラマンが「お前、イラクに入らないの?」って言うから、「ビザもないし、入れるわけないじゃん」って言ったら、「猪木のグループに入れといてやるよ」って言ってくれた。それで本社に電話して、「入れるみたいだから行きます」と。そうしたら、人質が解放されて大騒ぎになって、「またあいつニュースやってきた」ってことになっちゃったんです。
■戦場へ行くのはジャーナリストの生理
それでもう終わりだろうと思っていたら、湾岸戦争がいよいよ始まりそうな気配になった。それで編集局長から電話がかかってきて、「皆、行きたがらないんだ……お前しかいない」と。「戦争はすぐ終わるから、米兵が引き上げるところでも撮ってくれればいいから」と局長が言うから、しょうがないなと思って行ったら、カイロに着いたその日に開戦です。
次の日に現地のキャップが来て、「テルアビブにミサイルが落っこちた。君、行ってくれる?」と。しょうがないから行くわけだけど、着いたその晩にミサイルが落ちてきて、見に行って撮ったりしました。なんだか仕事的にはついているんですけどね。そこにいたのは朝日新聞とうちだけ。でも、朝日はすぐにエルサレムに引き上げて、僕も引き上げかなと思っていたら、「君はそこにいてくれ」と言うんです。「夕刊がよく売れるんだ」って。
そんな感じで、ゴタゴタがあったときに呼ばれるようになったんですよ。僕も嫌いじゃないんですよ、ああいう世界。けっこうやっていてだんだん面白くなってくる。やればやるほど面白いんだよね、危険な取材って。非日常の最たるものだから、高揚感もあるし。
実際、テルアビブにいたときに空襲警報が鳴ると防空壕に入っていたんだけど、だんだん嫌になってきた。テレビではCNNだけがバグダッドから中継していて、「ああ、あそこ行きたいなあ」と思い始める、人間の生理として。人間はもっと刺激を求めるみたいなところがありますよね。
だから僕は、戦争カメラマンは使命感で行っているなんていうのは違うと思う(そういう人もいるでしょうけれど)。そうではなくて生理として行くというのがあると思いますよ。麻痺もあるかもしれないけど、それだけ刺激が強いし、だんだんここまでは大丈夫という見極めの範囲が広くなってくるんです。だから面白いんだと思います。
■ジャーナリストは中立であるべきか?
僕はあまり中立と客観ということに興味がないんです。それよりも、僕は建前と本音という意識のほうが強くて、新聞は建前だと思っています。本や映画は本音でやります。
その違いは何かというと、読者の数です。新聞は最低100万人の人が見る。でも、本にしても映画にしても、1万いったら大喜びの世界です。コアな人たちが自分から進んで買ったり見にいったりするので、新聞みたいに向こうから来る媒体とは違う。
100万人以上いる媒体というのは、本音というか尖った意見は言えないですよ。人前で話す話と1対1で飲みながら話すのとでは違うわけですよ。それが100万人もいると、尖った意見を言ったときに大変じゃないですか。だから僕は、中立や客観というよりも、本音をどこまで出せるかどうか。
でもそれはある意味、仕方ないと思っているんです。100万人に向かって本音で言ったら大騒ぎなってしまうので、今ごろは首ですよね。公とプライベートという区別もあるし、そこの感覚を僕は使い分けています。新聞社も割合そこは分かっているでしょうね。新聞で本音を書くときは、別の意見を載せるとか、片方だけの意見を載せないというのは、新聞やテレビのポジションなんでしょう。
■メディアが伝える「危険」の裏側
イラク戦争終結の3ヵ月後に、小学2年生の娘をイラクに連れていったんですけど、僕としてはあの時期(一昨年の夏ですが)は、経験的に見ると全然危険ではないんです。
たしかにアメリカ兵は平均して毎日1人くらいは殺されていましたけど、日本人やほかの外国人は、あの時期誰も殺されていない。それをメディアは「イラクはまだ戦争中」と書くんです。それは米兵がやられているだけの話であって、我々もイラク人もやられない。
米兵に近づかなければ安全だと思ったし、米兵がやられたとしても、バグダッドというのは東京23区に近いくらいの広さなんです。そこで1人殺されたとしても、感覚としてはそれほど危険だということはないんです。
日本では「イラクは危ない」というイメージがあるから、そんなところになぜ小学生を連れていくんだというバッシングがありました。
でも、はっきりいって僕は、自分の現場感覚に自信があるから連れて行くわけです。だからメディアは正確じゃない。僕自身信じてないです。
オウムの地下鉄サリン事件が起きたとき、欧米のメディアが「日本の安全神話が崩れた」と書いたから、欧米人は日本に来なくなった。でも、僕らは翌日も地下鉄に普通に乗っているじゃないですか。メディアがそう書くのも分かる。でも現場は平然としているんです。
僕は、本当に危険だと思ったら、新聞社には聞かないです。聞かずに行っちゃう。たとえば(タリバン崩壊後の)一番危険だったカンダハルに行ったときも、朝日新聞の人は衛星電話で聞いていたけど、そんなことをやっていたら新聞社は困るんです。事情を言えば辞めておけとなっちゃうじゃないですか。
危険だと思ったときは、黙って入っておいて「カンダハルです」と。僕は、会社には黙って行くから便利だと思われてるんじゃないですかね。
■出たとこ勝負!
僕の映画の撮り方は、構成を決めずに行くから、いつも行き当たりばったりです。映画になるかどうかはいつも分からない。イラクで撮った『戦場の夏休み』という映画もそうでした。最初はひょっとしたらできるかなと思うので、いちおう試みるんです。
空港で娘にインタビューしています。「イラクについて何を知っているか」「怖くないか」とか。その時点はいいんだけど、イラクに入ったころには娘はうんざりしていました。暑さや疲れもあるから、インタビューしても何も答えない。だから僕も頭にきて、もういいって。子どもはそっちのけでイラク人を取材し始めたんです。
そうしたら、孤児院に行ったときに娘がそこの子どもたちと仲良くなり始めて、現地食なんか絶対食べなかったのに、向こうの子どもと一緒に食べ始めたんです。びっくりして撮ったんだけど、親としては感激ですよ。いつの間にかこんなに適応しやがってと。
その時点で、あ、これも映画に取り入れようと思っちゃたんですよね。それで子どもを入れた映画ができた。だから出たとこ勝負なんです。
【講師プロフィール】
吉岡逸夫(よしおか・いつお)
ノンフィクション作家・ドキュメンタリー映画監督・東京新聞記者。
愛媛県生まれ。青年海外協力隊としてエチオピアで活動後、コロンビア大学大学院修了。東京新聞にカメラマンとして入社後、記者に転じる。カンボジアやルワンダ、アフガニスタン、イラクなどを精力的に取材し、ノンフィクション作品を発表。近年は、ドキュメンタリー映画の制作・監督もこなす。
主な著書に『漂泊のルワンダ』(95年開高健賞、TBSブリタニカ)、『青年海外協力隊の正体』(三省堂)、『いきあたりバッチリ』(新潮社OH文庫)、『なぜ記者は戦場に行くのか』『イスラム銭湯記』(現代人文社)、『イラクりょこう日記』(妻詠美子さん・長女ふみさんとの共著、エクスナレッジ)、『人質』(郡山総一郎氏との共著、ポプラ社)、『なぜ日本人はイラクに行くのか』(平凡社新書)など。ドキュメンタリー映画に『アフガン戦場の旅』『笑うイラク魂』『戦場の夏休み』『人質』などがある。
ホームページはhttp://yoshi.net/...
Posted by 事務局 at [ セミナー報告 ]

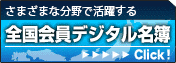
コメント